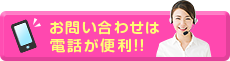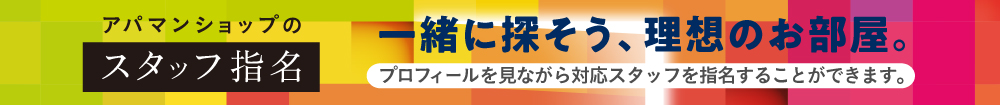若江城跡について

南北朝時代に築城されました
若江城跡は近鉄奈良線若江岩田駅から南へ15分ほど歩いたところにあります。
現在は城を思わせるものはありませんが、若江小学校の角にある神社に「旧若江城跡」の碑が、若江公民分館前には説明板があり、この一帯が若江城址になります。1972年からの発掘調査では若江公民分館周辺で2重の堀や井戸などの跡、瓦類・土器類・武器類など城の存在を裏付ける多数の資料が出土しています。
若江城は詳しい築城年代は解っていませんが、南北朝時代に幕府の命令により北朝方の拠点として河内国守護の畠中氏により築かれたとされており、200年余りの間河内国守護の政庁の役割をしていました。
若江城は周りを見渡すことが出来る小高い場所にあり、周辺は大和川の支流が網の目上に流れ、湿地や湿田に囲まれた天然の要害となっていました。
1400年代半ばから若江城主をめぐり畠中氏内でお家騒動が勃発し、これが応仁の乱の要因になりました。応仁の乱の後も家督争いは続き、次々と城主が入れ替わるうちに畠中氏の勢力が弱まり、三好氏が四国から河内平野に進出します。
その後三好氏が織田信長に破れ帰順し、信長の命により三好氏が若江城の城主となります。しかし三好氏が織田信長の怒りを買い攻められ、若江三人衆が内応して落城します。
三好氏の死後は若江三人衆の一人で熱心なキリシタンである池田丹後守教正が城主となりました。その際教会などを作ったことから八尾・岡山(今の四条畷)・三箇(今の大東)と並ぶ河内キリシタンの中心であったともいわれています。
織田信長の石山本願寺攻めの際は若江城が織田方の拠点となりました。
1581年に織田信長と石山本願寺の法主・顕如との和議が成立したため、若江城は八尾城に統合され廃城になったとされていますが、大阪城築城の際の記録には、若江城を破却し石垣や一部の建築物を移したとあり、その頃(1583)に廃城になったという説もあります。
若江城は資料が少なく、謎が多い城です。いつか若江城の歴史がわかる資料が見つかるといいですね。
執筆者:谷口 秋代