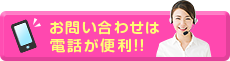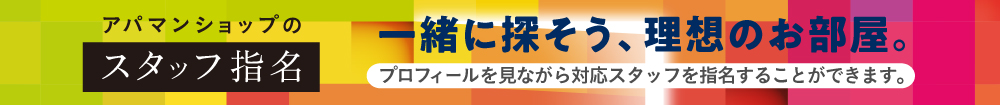地名の由来

中央総武線編
お茶の水
お茶の水駅は学生の街として知られています。
今回はこのお茶の水について調べてみました。
お茶の水の表記は「お茶の水」と「御茶ノ水」があります。
「お茶の水」と「御茶ノ水」の違いを皆さんはご存知でしょうか?
実はこの違いにも歴史的背景があるのです。
「お茶の水」は東京都千代田区神田駿河台から文京区湯島あたりまでの地域ですが、「御茶ノ水」という表記のしかたもあります。例えば、文京区と千代田区の境の神田川の南側のJR御茶ノ水駅を真ん中とし、その北にある、東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅、南にある、同地下鉄千代田線新御茶ノ水駅などです。
「お茶の水」と「御茶ノ水」の名前の由来は、どちらも江戸の始まりの頃に、外堀を掘るための神田山切り崩し中、高林寺の境内から水が湧き出し、その水を徳川家康のお茶をたてる水として献上したことが、そのままの字の如く地名の由来とされています。
お茶の水に東京師範大学、現在の筑波大学、女子師範学校が出来、勉学の街として知られていていました。現在でも、お茶の水女子大学や明治大学、いくつもの有名学校があります。学校名や企業・商業名などには、「お茶の水」の表記が使われている事がほとんどのようです。
このようなことから、基本的には、駅名などの表記の際には「御茶ノ水」の表記が使われています。道路標示や地域などの表記に関する名前、会社名だどには「お茶の水」の表記が使われるとされていると考えられます。
飯田橋の由来と似ている部分は、将軍の息のかかっているところです。
将軍に対して何かを行われる場所だったり、将軍ゆかりの地としての共通点があります。
執筆者:原啓太