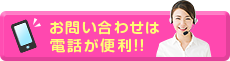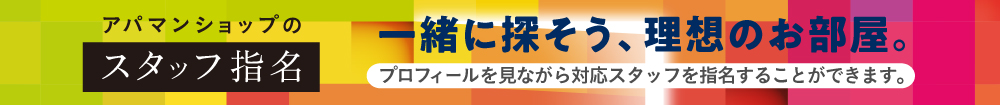実は博多が発祥だった!!

1年通して人気の麺類!
福岡だと博多ラーメンが真っ先に思い浮かぶ方も多いかもしれません。
これだけ暑いと温かい物より冷たいうどん、ざる蕎麦、そうめん、冷やし中華等の冷たい麺類が食べたいですね♪
そんな多くの人が好み様々なバリエーションや味付けで見た目でも舌でも楽しませてくれる麺類。
その中でも”うどん”や”蕎麦”は1年通して食べられる国民食としても挙げられる料理ですが、【博多発祥】って知っていました?
その他にお茶や饅頭なども博多発祥なのですが今回はどのようにして伝わって来たのかをご紹介します。
博多祇園山笠発祥のお寺にその石碑はあります!!
博多駅から徒歩5分程の場所に”博多祇園山笠発祥のお寺”と呼ばれる【浄天寺】はあります。
この浄天寺、なんと山笠だけでは無いんです!
その境内には【饂飩蕎麦発祥之地】と刻まれた石碑があるんです!(うどん、そば発祥の地)うどんは何となく聞いた事ありましたが、まさかのそばまで・・・。
この浄天寺は博多駅の博多口を大博通り沿いに5分程歩いた所にあります。
このお寺が開かれた当時(1200年代)は沢山のお坊さんが中国に色々な技術の他、書物などを学びに行き、それを持ち帰っていたそうです。
1241年に中国から他のお坊さんのように色々な知識を持ち帰った後の承天寺を開いたお坊さん【聖一国師】と言う人が持ち帰った技術により、穀物から細やかな粉を作れるようになったそうです。
その後に”うどん”や”そば”などが出来たとされています。
今やどこでも食べる事の出来る、うどんやそばが全国に広まったのはこのお坊さんのおかげなんですね♪
ちなみにこのお坊さんは”うどん”や”そば”だけじゃなく”饅頭”の作り方も広めたそうで、饅頭は茶道が発展した鎌倉時代に全国にお茶菓子として共に広がっていったそうです。
それにしても当時のお坊さんは今のように映像で残す技術が当然ながら無い時代で仏教を学ぶだけでなく食文化等の海外の技術まで学んで来て、さらに人に伝える事まで出来る本当にスゴイ人達であったんだと感心しました。
ちなみに2008年には【饅頭発祥の碑】も建てられているんですよ!
博多に寄られた際には是非行ってみて下さい。
執筆者:仁田原 大輔