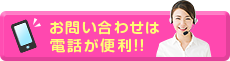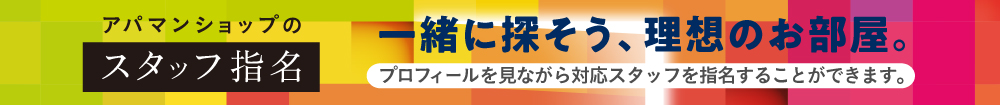千手寺について

千手寺のご紹介です
多くの文化財が保存されています
千手寺は今から約1300年前、笠置山千手窟で修行していた役行者(えんのぎょうじゃ)が不思議な神光の導きによってこの地に至り山を開いて建立した事が始まりと伝えられています。
その後、空海(弘法大師)がが千手観音を本尊として中興したそうです。惟喬(これたか)親王の乱で出火消失し、本尊の千手観音が自ら深野池に飛入し行方がわからなくなりましたが在原業平(ありわらのなりひら)が池の中で光る千手観音を発見して、5院を建立したといわれ、在原業平の腰掛石や五輪塔、業平廟などが残っています。
この寺は河内平野を一望する立地で、光堂と呼ばれる本堂を中心に中世には修験道の霊場として、また夕日を望み極楽に往生を願う迎接堂として人々の信仰を集めてきました。
寺宝として、本尊千手観音立像・絹本著色不動明王画像・密教法具(いずれも東大阪市指定有形文化財)や木造不動明王座像(大阪府指定有形文化財)など、多くの文化財がのこされています。
境内には大正時代に「そろり」という落語家が芭蕉の句をもじってつくった「業平と背中合わせのぬくさかな」という歌碑があります。また、本堂の裏には古墳時代後期の横穴式石室が保存されており、見学することが出来ます。
千手寺は近鉄石切駅から歩いて5分ほどの場所にあります。
周辺には旧生駒トンネルや聖徳太子が創建したと伝えられる大龍禅寺、旧河澄家、石切劔箭神社などがありますので、東大阪にお住まいの方もそうでない方も、石切の町を歩きながら歴史探訪を楽しんでみてはいかがでしょうか?
執筆者:谷口 秋代