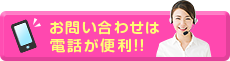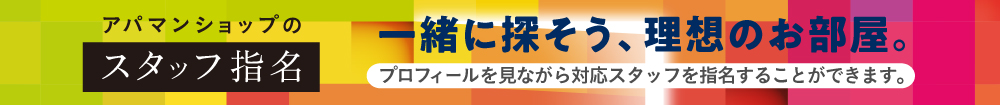諏訪神社について

市内最古の建立年代が明らかな神社建築です
諏訪神社は近鉄けいはんな線 吉田駅から北西へ約600mの場所にひっそりとたたずむ神社です。
この神社は、本殿に残されていた古文書によると、天文元年(1532年)、信濃国諏原之庄の諏訪連(すわのむらじ)の子孫たちがこの地に村を開き、諏訪大明神、稲荷台明神、筑波大権現の三社を勧請したとされ、社名の由来となっています。
現在は三社のうちすわ大明神を祀る一社だけが残され、大切に保存されています。
本殿は一間社流造の杮葺き(こけらぶき)で、社殿の大きさに比べて柱や梁が太く、室町時代末期の建築様式の特徴がみられます。本殿には当時の彩色が残っているそうです。
庇(ひさし)や身屋の四周に写実的な花鳥彫刻を持つ蟇股(かえるまた)を入れるなど桃山様式の特徴が混在することから、江戸時代に大改修が行われたことが伺えますが、全体的に室町様式がよく残されています。
諏訪神社は建立年代が明らかな市内最古の神社建築であること、中新開の歴史を伝える貴重な記念物であることから東大阪市の文化財に指定されています。
ちなみに、諏訪大明神は建御名方神(タケミナカタ)の別名で、南宮大明神(ナングウダイミョウジン)とも呼ばれます。
日本三軍神のひとつとされ、また農業神、狩猟神を司るとも言われています。
執筆者:谷口