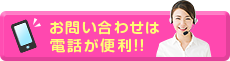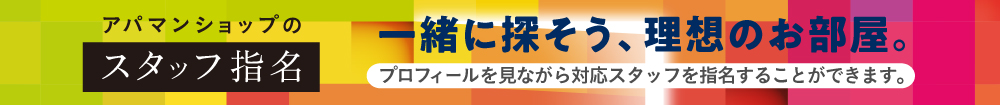日本三大八幡宮の歴史

代表的なお祭りの背景には、こんな歴史があったのです。
福岡が誇る三大八幡宮。広い境内でとても心が清まります☆
我らが福岡の筥崎宮!!☆
楽しそうなお祭りがありました。
私も秋に開催される放生会しか知りませんでした。
梅雨時期が終われば、みなさんが大好きな放生会が始まりますよ!!
大々的な見世物等もありますし、夏の思い出で行ってみてください。
さて、少し話がずれましたが本日は筥崎宮の歴史についてお話させて頂きたいと思います。
まず、このあたりに【筥松】という地名があります。
地名の由来は、楼門そばの玉垣で囲まれた松の木からきているそうです。
応神天皇がお生まれになったときのエナを箱に入れ、この地に納めた印として植えられた木であるといわれております!!
もともとこの地は違う名称で呼ばれていましたが、この箱が納められたことで【箱崎】と呼ばれるようになったそうです☆
ここで補足!!!
先程の説明の中で【楼門】というキーワードが出てきたと思いますが覚えていますか?!
【楼門】についてご説明させて頂きます!
1594年筑前の小早川隆景が建てました。
少し固い言葉がたくさん出てきておりますが、要するに、ものすごく豪華な造りの建物だということが言えますね。
この楼門の扉は紋様彫刻で江戸時代に有名な方が作ったということでとても有名になっています。
続いて本宮の鳥居について勉強しましょう!!
本宮の鳥居は本殿近くより一之鳥居、二之鳥居と呼ばれています。
一之鳥居は1609年に藩主黒田さんが建てたといわれています。
この鳥居の柱は三段に切れていることが珍しいところだそうです。
正直、私はそこまで見たことがありません!!
今回この投稿の際に調べていて知りました。
今度放生会で筥崎宮に行ったら、いろいろと注目してみたいと思います☆
是非、みなさんも少し変わった目線でご覧になって下さい。
さて、歴史にまつわる知識をご紹介させて頂きましたが、少し固い内容でしたでしょうか?
こういう歴史を少し知識に入れると、普段の景色が少し変わった目線で見ることが出来るかと思います。
学生時代歴史が得意では無く、勉強から遠ざかってきた私ですが、社会人になり自然と学ぶことが増えてきました。
テレビや雑誌、先輩からの雑談等で知識として頭に入ってくる情報は、今後意外と役に立つ情報盛りだくさんですよ☆
皆さん、毎日雑学一つ頭に入れ、普段の会話でさらっと使えるかっこ良い社会人目指して、頑張りましょう☆
執筆者:井上 亮