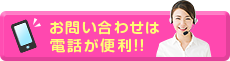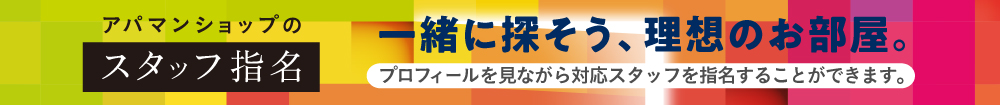11月の異名について

霜月以外にも色々な呼び方があります
11月も終わりに近づいてきました。
東大阪では今年は秋を感じる日が多かった印象がありますが、この頃はぐっと気温が下がり、街ではクリスマスの飾りを
見かけることも多くなりすっかり冬らしくなってきました。
11月の別の呼び方といえば有名なのは「霜月」かと思いますが、霜月の他にも様々な異名があるようです。
今回は11月の異名とその意味・由来について調べてみました。
「霜月(しもつき)」
霜が降りる月という意味です。
「神帰月(かみきづき)」
10月に出雲大社に集まった神様が帰ってくる月という意味です。
「神楽月(かぐらづき)」
収穫感謝と来年の豊作を願い神楽が催されていたことから。神楽とは神前で演奏する舞楽のことです。
「建子月(けんしげつ)」
「建」の字は北斗七星を表します。また「おざす」と読み、「尾指す」の意味があります。
北斗七星の柄杓のような形の柄の部分(尾)が子の方角(12時の方角・北)を指すことからこう呼ばれます。
12月は「建丑月」・1月は「建寅月」など1~12月それぞれに建の字の後に干支が入る呼び方があります。
「雪待月(ゆきまちづき)」
冬籠りをする前の雪を待つ月という意味です。
その他に「竜潜月(りゅうせんげつ)」「子月(ねづき)」「辜月(こげつ)」「天正月(てんしょうげつ)」
「陽復(ようふく)」等・・・
上記以外にもたくさんの異名があるようです。
元々は旧暦の11月を表す呼び方なので、現在の11月に使うには少し早い感じがしますね。
執筆者:谷口