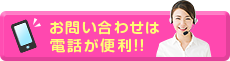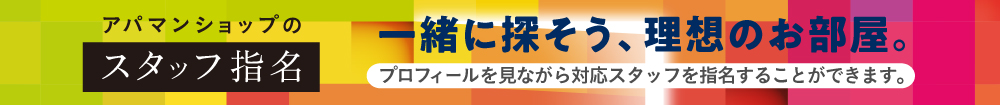片付けられない人が実践すべき片付け術6選、今日から片付けられる人になる!

「部屋を片付けたいけれど、どこから手をつけていいかわからない」「せっかく部屋を掃除してもすぐにごちゃごちゃしてしまう」そんな悩みを抱えてはいませんか?
片付けができていないお部屋では、失くし物や探し物に時間を取られてしまったり、生活のパフォーマンスが落ちてしまったりと時間やお金を無駄にしてしまうことにもなりかねません。片付け術をマスターして、片付け上手を目指しましょう。
片付けられないなら散らからないようにすればいい
実は、片付けられない人には、ある共通点があります。それを知ることで、片付けへの意識を変えることができます。いったいどんな特徴があるのでしょうか?見ていきましょう。
モノが捨てられない
「いつか使うかもしれない」「高かったから捨てるのはもったいない」「かわいい箱だからとっておこう」…。モノを手にした時、ついついそんな思いになって「捨てられない」ということはありませんか?モノを大切にするのはいいことですが、残しておいたモノを使う機会はあまり訪れないものです。
1年以上使っていないモノがあるのなら、処分を考えてみるべきです。フリマアプリなどを利用して、必要としてくれる人の手元に届けるという手もあります。
衝動買いをしてしまう
安い、期間限定、いつか使えそう、などを理由に衝動買いしてしまうのも、片付けられない人の特徴です。実は使っていないモノ、買ってみたけれど使えていないモノが部屋の中にありませんか?買い物をした瞬間は「いい買い物をした!」と思ってしまいがちですが、実際に使えていないのなら、いい買い物とは言えませんよね。
衝動買いをしないためには、「欲しいものリスト」を作ることも有効です。欲しいものをリスト化して、一定期間経過してから「本当に欲しいのか?必要なものなのか?」を判断します。しっかりと考えてから買うことができるので、モノを増やすことを避けられます。無駄遣いの防止にもなるので一石二鳥です。
片付けを「あとでまとめて」やろうとする
片付けや掃除を「あとでまとめてやろう」と考えるのも、片付けられない人の特徴です。一気にまとめて片付けた方が効率的と考えてしまうかもしれませんが、実は先送りにしているだけなのです。
結局、片付けなければいけない範囲が広がってしまい時間も労力もかかり片付けへのモチベーションが下がってしまいます。片付けは日頃から、コツコツやるようにしましょう。片付けが苦手、片付けができないと考えている人は、まず「散らからない部屋」を目指してみることをおすすめします。
「散らからない部屋」の基本は、モノを捨てる・増やさないことです。無駄なモノを持たない、モノの定位置を決めるなど、ちょっとした工夫で「散らからない部屋」を実践することができます。自分が選んだ、大切なモノに囲まれた暮らしになるので、モノへの意識も自然と変わっていきそうですね。
片付けられない人が実践すべき片付け術

片付けができない人が今日から実践できる片付け術をご紹介します。モノへの意識を変えるだけで、片付けが苦ではなくなるはずです。すぐに実践して、片付け上手になりましょう。
モノを仕分けする
まずは自分が持っているモノを把握しましょう。収納されているすべてのモノを出し、「日常的に使っている」「使っていないから処分する」「使っていないけれど処分するか迷う」の3つに仕分けます。
ポイントは、「使っていないけれど処分するか迷う」モノをひとつにまとめて、目につくところに一定期間置いておくことです。数週間後に改めて見て「なくても困らない」「使う機会がなさそう」と思ったら処分してしまいましょう。
モノを捨てる
モノを仕分けた際に「いらない」と感じたものは思い切って処分しましょう。思い出の品や高価なものは処分しにくいですが、必要ないと感じているのなら、必要としている人に譲った方がモノも喜ぶはずです。どうしても残しておきたい場合は写真などを撮ってデータで残しておきましょう。
モノを減らすことで片付けがしやすくなり、心地よい空間を保てるようになります。心地よい空間を持続させるためにさらに片付けが楽しくなり、好循環が生まれていきます。
モノをシンプルに収納する
必要なモノの収納は、できるだけシンプルにしましょう。「見せる収納」などオシャレな方法もありますが、ハードルが高く持続させるのが難しいため、収納初心者には向いていません。まずはシンプルに、片付けが習慣となるような収納方法からはじめましょう。
収納の基本は、頻繁に使うものを手に届きやすく目につくところにしまうことです。「使ったあとはすぐに片付ける」という当たり前のことが簡単にできる収納を目指しましょう。
さらに、モノが探しやすいというのも大切なポイントです。透明の収納ケースを使うなど、どこに何があるのかすぐにわかるような工夫をすることで、片付けへの心理的なハードルを下げることができます。
モノの定位置を決める
モノの定位置が決まっていないと、失くし物や探し物の原因となります。鍵は玄関先、スマホはベッドサイドなど使ったら必ず戻す定位置を決めておきましょう。生活動線を考えて、モノの定位置を決めることでストレスも少なくなります。忘れ物が多い人も、外出時に慌てることがなくなるでしょう。
モノを床に置かない
定位置が決まっていないモノを「とりあえず」床に置いていませんか?「とりあえず」のつもりがそのまま放置され、片付けられない原因となってしまう場合があります。床の上にモノがあると掃除がしにくく、衛生的にもよくありません。
またすぐに使うモノの「とりあえず」の置き場所としては、大きめのカゴを用意するのが良いでしょう。床にモノがなくなるとそれだけで片付いた部屋に見えます。
モノを循環させる
モノの循環とは、「ひとつ買ったらひとつ手放す」ことを指します。部屋の中にあるモノの量を一定にすることで片付けのハードルは下がります。本当に必要なものだけを買うようになるので節約にもつながり、生活がシンプルになっていくでしょう。モノを増やさないという意識を持つことが大切です。
ルールを決めれば片付けが楽にできる
自分なりの片付けルールを決めることで、片付けはもっと簡単に、もっと楽しくなるはずです。
例えば、買い物をするときは必ず「欲しいものリスト」をつくって、1ヶ月検討してから購入する・ひとつのモノを処分してから新しいモノを買うなど、自分なりの簡単なルールを決めてみるのがいいでしょう。
また、片付けができない人に多いのが、「こうしなければいけない」という高い理想を求めるが故に、理想通りに片付けができないこと自体にストレスを感じてしまうというパターンです。
まずは「片付けが楽にできる部屋」=「散らからない部屋」を目指しましょう。片付けがストレスにならないように、1日ひとつ、いらないものを捨てていくなどハードルの低いルールからはじめてみることをおすすめします。
おわりに
モノが多い状態から「片付け」を考えると億劫に感じてしまうものです。まずはモノを減らす努力からスタートさせ、本当に必要なものを選択し、手元に残すようにしましょう。
大切なモノに囲まれた暮らしはシンプルながら豊かで、心地の良いものです。モノを手放すことでモノへの意識が変わっていくのではないでしょうか。
片付けられた部屋は、そこにいるだけで、スッキリと清々しい気持ちになれます。空間に余裕ができると、心にも余裕が生まれるのかもしれませんね。
執筆者:編集部